3月25日に芝浦工業大学で開催された第42回化学クラブ研究発表会について坪村太郎会員からの報告です。
日本化学会には各地方に支部があり、それぞれ独自の化学振興活動を行っています。関東支部では、以前より毎年3月に中学、高校の化学関連クラブの発表会を行っていて、私はコメンテータの一員として何回か参加しております。
芝浦工業大学豊洲キャンパスで開催された本年度の今年度の発表会には、口頭発表とポスター発表合わせて50件以上の発表がなされました。会場は熱気に包まれ、特にポスター会場では高校生同士の議論が各所で行われている様子が見られました。ビスマス結晶や太陽電池の作成などポピュラーなテーマから、コオロギ中のタンパク質や人工イクラなどユニークなテーマまで、様々なテーマに一生懸命取り組んでいる様子が見られました。特に近年はエコを意識したテーマ(たとえば割り箸から紙を作るとかプラスチックのリサイクルとか)も多く見られます。
どれも様々な研究を楽しそうにやっている様子が目に浮かぶような発表で、頼もしく感じました。大学の先生に協力していただき、吸収分光器からNMRまで最新の装置を使ったような研究もいくつか見られ、びっくりした次第です。ただ、いくつか気になる点もありました。一つは再現性の問題です。条件に左右されそうな実験では再現性を確認することは重要です。また、(なかなか難しいですが)論理的に結論を出す練習をもう少し積めばさらに良くなるのにと思う研究もありました。さらにポスター等を誰が見てもわかりやすく作ることも課題かもしれません。
今回金賞・銀賞・銅賞をはじめ各種の賞が優れた発表に授与され、それらの発表は立派なものでありました。受賞は逃したものにも、優れたものが多く見られたことも補足しておきたいと思います。日本の研究力の衰えがよく言われる昨今ですが、彼らに大いに期待したいと思います。


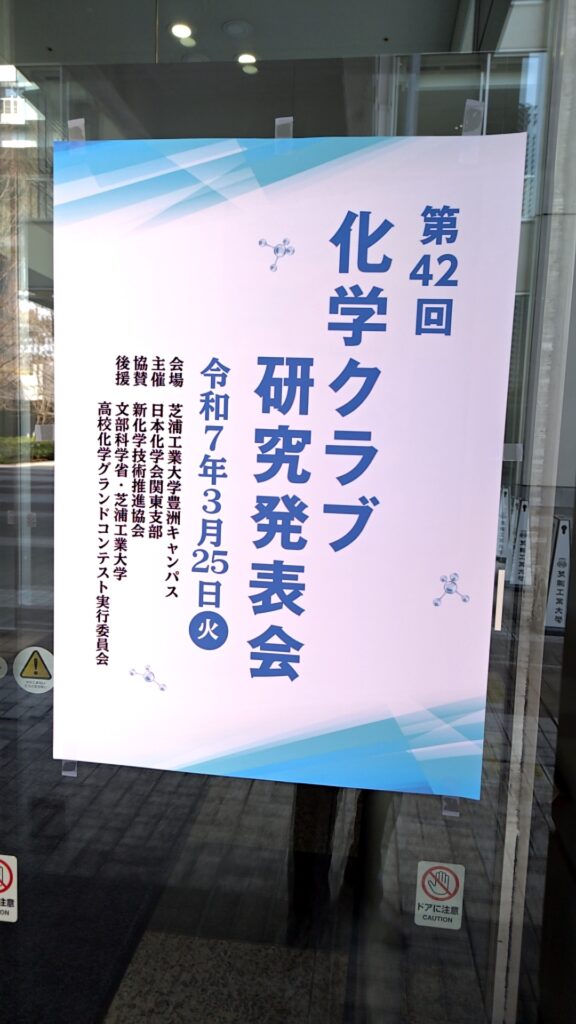





 Views Today : 19
Views Today : 19